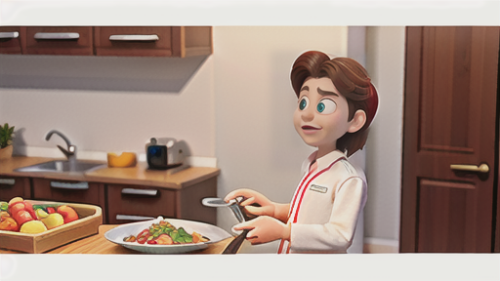魚介類
魚介類 車海老の魅力:高級食材の秘密
水族館や食卓で私たちの目を楽しませてくれるエビ。その種類は実に豊富で、日本の周りの海だけでも二百種類ほどが生息しています。大きく分けて、海底を歩くのが得意なグループと、水中を泳ぐのが得意なグループの二つに分けられます。
歩くのが得意なグループには、イセエビやザリガニなどがいます。大きなはさみを持ち、海底を歩き回って暮らしています。一方、泳ぐのが得意なグループには、クルマエビ、コエビ、オトヒメエビなどがいます。彼らは体を使って上手に泳ぎ、水中を自由に動き回ります。
今回紹介するクルマエビは、泳ぐのが得意なグループの中のクルマエビの仲間です。名前の通り、車のように活発に動き回る性質を持っています。そのため、水槽などで飼うのはなかなか難しいと言われています。水槽の中を縦横無尽に泳ぎ回り、じっとしていない様子が目に浮かびますね。
また、クルマエビは水中に卵を産み落とすという特徴も持っています。そのため、卵を抱えたメスを見る機会はあまりありません。産み落とされた卵は水中で孵化し、小さなクルマエビが誕生します。
一方、同じ泳ぐのが得意なグループのコエビの仲間は、卵を抱えるという習性があります。お腹にたくさんの卵を抱え、大切に守る様子は、水族館でもよく観察されます。コエビの仲間には、甘エビとして知られるホッコクアカエビや、縞エビと呼ばれるモロトゲアカエビなどがいます。これらは私たちにも馴染み深い、食卓によく並ぶエビです。このように、エビの種類によって、その生態や特徴は実に様々です。色々なエビについて調べてみると、新しい発見があるかもしれません。