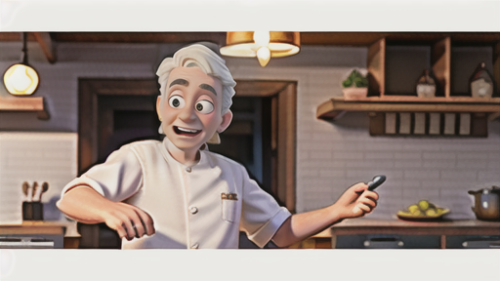揚げる
揚げる 下揚げのコツ:おいしさアップの調理法
下揚げとは、食材に軽く火を通すため、短時間油で揚げる調理法のことです。仕上げに別の調理を行う二段階調理の下ごしらえとして用いられます。例えば、衣をまとった天ぷらや唐揚げをカリッと仕上げるために二度揚げする場合の最初の揚げ工程、あるいは煮物を作る際に、根菜類などの食材をあらかじめ油で揚げておく工程などが、下揚げにあたります。
一見、手間が増えるように感じますが、下揚げには様々な利点があります。まず、食材の表面を油でコーティングすることで、うまみを閉じ込めることができます。例えば、ジャガイモを下揚げしてから煮物にすると、煮崩れを防ぎ、ホクホクとした食感を保つことができます。また、肉や魚を下揚げしてから煮たり焼いたりすると、余分な脂を落とし、風味を閉じ込めることができます。
次に、食材の色味を美しく保つ効果があります。例えば、ナスやピーマンなどの野菜は、下揚げすることで鮮やかな緑色や紫色を保つことができます。また、下揚げした食材は、表面が油でコーティングされるため、後の調理工程で味が染み込みやすくなります。煮物の場合は、味が均一に染み渡り、短時間で仕上げることができます。
さらに、下揚げは調理時間の短縮にも繋がります。食材にあらかじめ火を通しておくことで、仕上げの調理時間を大幅に短縮できます。例えば、肉や魚などは、下揚げしてから煮たり焼いたりすることで、中心まで火を通す時間を短縮できます。
下揚げする際の油の温度と時間は、食材の種類や料理によって異なります。一般的には、高温で短時間揚げるのが基本です。低い温度で長時間揚げると、食材に油が染み込みすぎてベタベタになったり、逆に焦げてしまったりすることがあります。適切な油温を保つためには、温度計を使う、揚げる食材の量を調整するなどの工夫が必要です。焦げ付きを防ぎ、食材の中まで均一に火を通すために、油温管理は大切なポイントです。