万能鍋、行平鍋を使いこなそう!

料理を知りたい
先生、『行平鍋』ってどんな鍋ですか?普通の鍋とどう違うんですか?

料理研究家
良い質問だね。『行平鍋』は、金属でできていて、片側か両側に注ぎ口がついているのが特徴だよ。取っ手は木製で、底が丸みを帯びているものが多いね。煮物や汁物を作るのに向いているよ。普通の鍋と比べると、注ぎ口があるから汁物を移し替えやすいんだ。

料理を知りたい
なるほど。注ぎ口があるんですね。アルミ製のものが多いって聞いたんですけど、他の素材のものもあるんですか?

料理研究家
そうだね、アルミ製は軽くて扱いやすいから家庭ではよく使われているね。他にも銅やステンレスのものもあるよ。銅製は熱伝導が良いから、プロの料理人がよく使っているんだ。ステンレス製は錆びにくくて丈夫だよ。
行平鍋とは。
木の取っ手がついた、ほどほどの深さのある金属製の鍋で、叩いて作られた和風の鍋のことを『行平鍋』といいます。片側、あるいは両側に注ぎ口がついています。家庭では、アルミ製のものが使いやすく、大きさの違うものを2~3個用意しておくと便利です。
行平鍋とは

行平鍋とは、日本の台所で長年親しまれてきた、使い勝手の良い調理道具です。その歴史は古く、江戸時代から使われていたという記録も残っています。名前の由来は諸説ありますが、一説には、関西地方で「行平」と呼ばれていた行商人が使っていたことから、その名がついたと言われています。
行平鍋の最大の特徴は、ハンマーで叩いて成形する打ち出し加工によって生まれる、独特の凹凸模様です。この模様は単に見た目の特徴であるだけでなく、強度を高める効果もあります。また、表面積を広げることで熱伝導率を向上させ、食材に熱が均一に伝わるため、美味しく仕上がります。さらに、この凹凸のおかげで食材が鍋底にこびりつきにくくなるという利点もあります。
行平鍋のもう一つの特徴は、鍋の縁に一つ、あるいは両側に付いている注ぎ口です。この注ぎ口は、汁物や煮物を器に移す際に、液だれを防ぎ、スムーズに注げるように工夫されています。汁切れが良いため、料理を美しく盛り付けることができます。
行平鍋の素材は、主に金属が使われています。家庭でよく使われているのは、軽くて扱いやすいアルミ製です。熱伝導率が良いので、短時間で調理することができます。プロの料理人が使うような銅製の行平鍋は、熱伝導率がさらに高く、繊細な火加減の調整が求められる料理にも最適です。近年では、ステンレス製の行平鍋も人気を集めています。耐久性に優れ、錆びにくいのが特徴です。
多くの行平鍋の持ち手は木製です。木は熱が伝わりにくい素材なので、調理中に持ち手が熱くなりすぎるのを防ぎ、安全に調理することができます。
行平鍋は、煮物、汁物、揚げ物など、様々な料理に使える万能鍋です。味噌汁や煮魚などの和食はもちろん、カレーやシチューなどの洋食にも使うことができます。一つ台所に置いておけば、料理のレパートリーが広がること間違いなしです。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 歴史 | 江戸時代から使われている |
| 名前の由来 | 行商人が使用していたからという説がある |
| 打ち出し加工 | 凹凸模様が強度を高め、熱伝導率を向上させ、食材がこびりつきにくくする |
| 注ぎ口 | 汁切れが良く、液だれを防ぐ |
| 素材 | アルミ製(軽量)、銅製(高熱伝導率)、ステンレス製(耐久性) |
| 持ち手 | 木製(熱が伝わりにくい) |
| 用途 | 煮物、汁物、揚げ物など多様な料理に使える |
大きさの種類

行平鍋を選ぶ際、大きさは重要な要素です。行平鍋には実に様々な大きさがあり、用途に合わせて使い分けることで、より快適に料理を楽しむことができます。
例えば、味噌汁や少量の煮物、ちょっとしたおかずを作りたい時などには、小さめの行平鍋が便利です。少量の調理にちょうど良い大きさなので、無駄なく食材を使い切ることができます。また、一人暮らしの方や、少量ずつ料理を作りたい方にもおすすめです。コンパクトなので、コンロの上でも場所を取らず、収納にも困りません。
一方、大人数分の煮物や、カレー、シチュー、麺類を茹でる時などには、大きめの行平鍋が活躍します。たっぷりの量を一度に調理できるので、大人数での食事や、作り置きをする際に便利です。また、具材をたくさん入れても、鍋の中で窮屈にならず、しっかりと火を通すことができます。
一般家庭では、2~3種類の大きさの行平鍋を揃えておくと、様々な料理に対応できて便利です。例えば、一人分のインスタントラーメンを作るのにちょうど良い小鍋、カレーやシチューなどの煮込み料理に使える中くらいの鍋、そして大人数分の料理や麺茹でなどに使える大鍋があると、日々の料理がよりスムーズになります。
行平鍋を選ぶ際には、収納スペースも考慮することが大切です。様々な大きさの行平鍋を揃えたい気持ちはあっても、収納スペースが限られている場合は、無理のない範囲で揃えるようにしましょう。使う頻度や、作る料理の種類などを考えて、自分に合った大きさの行平鍋を選ぶことが大切です。
| 行平鍋の大きさ | 用途 | メリット | おすすめの人 |
|---|---|---|---|
| 小さめ | 味噌汁、少量の煮物、少量のおかず | 無駄なく食材を使い切れる、コンロの上で場所を取らない、収納に困らない | 一人暮らしの方、少量ずつ料理を作りたい方 |
| 大きめ | 大人数分の煮物、カレー、シチュー、麺類を茹でる | たっぷりの量を一度に調理できる、具材をたくさん入れても窮屈にならない | 大人数での食事が多い方、作り置きをする方 |
| 小鍋 | 一人分のインスタントラーメン | – | – |
| 中くらいの鍋 | カレーやシチューなどの煮込み料理 | – | – |
| 大鍋 | 大人数分の料理や麺茹で | – | – |
行平鍋のお手入れ

行平鍋は、毎日のお料理で活躍してくれる頼もしい調理器具です。しかし、その扱い方を間違えると、せっかくの使い勝手の良さが失われてしまうこともあります。そこで、今回は行平鍋を長く愛用するための、お手入れ方法を詳しくご紹介します。
行平鍋を使った後は、なるべく早く洗うことが大切です。食べ物の汚れや油分がこびり付く前に、ぬるま湯でさっと洗い流しましょう。洗う際には、研磨剤入りの洗剤や金属たわしは使わないようにしてください。行平鍋の表面に傷が付き、そこから錆びが発生する原因になります。柔らかいスポンジと中性洗剤を使って、優しく丁寧に洗いましょう。特に鍋底の外側は火に直接当たるため、焦げ付きやすい部分です。焦げ付きが酷い場合は、無理に落とそうとせず、お湯を沸かして焦げを柔らかくしてから落とすのがおすすめです。鍋に水を張り、重曹を大さじ一杯ほど入れて沸騰させると、焦げ付きが浮いてきますので、その後スポンジで優しく落とします。
洗い終わったら、すぐに水気を拭き取ることが重要です。行平鍋は鉄でできているため、濡れたまま放置すると錆びてしまいます。清潔な布巾でしっかりと水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させましょう。木製や樹脂製の柄が付いている場合は、特に注意が必要です。柄の部分は水に弱いため、長時間水に浸したり、濡れたまま放置すると劣化の原因になります。柄の部分も丁寧に拭き、乾燥させてください。
正しいお手入れを続けることで、行平鍋は一生ものとして長く活躍してくれます。焦げ付きや錆びを防ぎ、使い始めのような輝きを保ちながら、美味しい料理を作り続けていきましょう。毎日の少しの手間を惜しまずに、行平鍋を大切に使いましょう。
| お手入れ手順 | 詳細 |
|---|---|
| 使用後 | なるべく早く洗う。食べ物の汚れや油分がこびり付く前に、ぬるま湯でさっと洗い流す。研磨剤入りの洗剤や金属たわしは使用しない。柔らかいスポンジと中性洗剤を使って、優しく丁寧に洗う。 |
| 焦げ付き対策 | 鍋底の外側は特に焦げ付きやすいので、焦げ付きが酷い場合は、無理に落とそうとせず、お湯を沸かして焦げを柔らかくしてから落とす。鍋に水を張り、重曹を大さじ一杯ほど入れて沸騰させると、焦げ付きが浮いてくるので、その後スポンジで優しく落とす。 |
| 洗い終わった後 | すぐに水気を拭き取る。行平鍋は鉄でできているため、濡れたまま放置すると錆びてしまう。清潔な布巾でしっかりと水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。木製や樹脂製の柄が付いている場合は、特に注意が必要。柄の部分は水に弱いため、長時間水に浸したり、濡れたまま放置すると劣化の原因になる。柄の部分も丁寧に拭き、乾燥させる。 |
様々な料理に

行平鍋は、和食だけでなく、様々な料理に使える万能な調理器具です。その汎用性の高さは、毎日の料理を楽しく、そして手軽にしてくれます。一つ持っていれば、様々な料理に挑戦できることでしょう。
まず、行平鍋は煮物や汁物作りに最適です。程よい深さと丸みのある形状は、食材を優しく包み込み、じっくりと味を染み込ませます。例えば、肉じゃがや筑前煮などの定番料理はもちろん、季節の野菜を使った煮物にもぴったりです。素材本来の味を活かした、滋味深い一品が作れます。
揚げ物にも行平鍋は活躍します。少量の油で揚げ焼きをする際に、行平鍋の傾斜が役立ちます。油が鍋底に自然と集まるため、少ない油でも食材全体をカリッと揚げられます。例えば、鶏肉の唐揚げや野菜の素揚げなど、手軽に揚げ物が楽しめます。油の処理も簡単なので、後片付けの手間も省けます。
麺類を茹でるのにも、行平鍋は便利です。うどんやそば、そうめんなど、様々な麺類を茹でられます。注ぎ口が付いているので、茹で汁を捨てるのも簡単です。また、野菜を茹でるのにも使えます。ほうれん草やブロッコリーなど、お好みの野菜をさっと茹でることで、栄養を逃さず美味しくいただけます。
行平鍋でご飯を炊くことも可能です。熱伝導率の高さから、短時間でふっくらと炊き上がります。お米の粒が立ち、一粒一粒がしっかりと感じられる、美味しいご飯が楽しめます。少量のご飯を炊きたい時にも重宝します。
このように、行平鍋は、煮る、揚げる、茹でる、炊くなど、様々な調理方法に対応できる万能鍋です。一つあるだけで、料理の幅が広がります。ぜひ、行平鍋を使って、色々な料理に挑戦してみてください。
| 調理方法 | 料理例 | メリット |
|---|---|---|
| 煮る | 肉じゃが、筑前煮、季節の野菜の煮物 | 食材を優しく包み込み、じっくりと味を染み込ませる |
| 揚げる | 鶏肉の唐揚げ、野菜の素揚げ | 少量の油で揚げ焼きができる、油が鍋底に自然と集まる、油の処理が簡単 |
| 茹でる | うどん、そば、そうめん、ほうれん草、ブロッコリー | 注ぎ口が付いているので茹で汁を捨てるのが簡単、栄養を逃さず美味しく茹でられる |
| 炊く | ご飯 | 熱伝導率が高く短時間でふっくらと炊き上がる、少量のご飯を炊くのに便利 |
行平鍋を選ぶ時のポイント

行平鍋を選ぶ際には、いくつか大切な点があります。まず大きさです。作る料理の量や家族の人数によって選ぶ大きさが変わってきます。大家族やたくさんの料理を作る機会が多い方は、大きめの行平鍋を選ぶと一度にたくさんの調理ができて便利です。ですが、大きすぎると収納場所に困ったり、洗うのが大変になることもあります。一人暮らしの方や少量の料理を作る場合は、小さめの行平鍋が適しています。小さすぎると吹きこぼれの原因となるので、作る料理の量に合った適切な大きさを選びましょう。
次に素材です。行平鍋には様々な素材のものがありますが、代表的なものは軽くて熱伝導率が高いアルミ製と、丈夫で焦げ付きにくいステンレス製です。アルミ製の行平鍋は火の通りが早く、短時間で調理できますが、熱伝導率の高さゆえ焦げ付きやすいという側面もあります。こまめにかき混ぜたり、火加減に注意する必要があります。一方、ステンレス製の行平鍋はアルミ製のものより重く、熱伝導率は低いですが、耐久性が高く焦げ付きにくいのが特徴です。焦げ付きにくいので、煮込み料理などにも向いています。最近では、アルミとステンレスの複数層構造になっているものもあり、それぞれの素材の利点を兼ね備えています。
取っ手の素材にも注目しましょう。木製や樹脂製の取っ手は熱くなりにくく、素手で持つことができます。金属製の取っ手は丈夫ですが、加熱すると高温になるため、ミトンなどが必要です。また、蓋の形状も重要です。全体を覆うタイプの蓋は、しっかりと熱を閉じ込め、煮込み料理などに適しています。落とし蓋は、食材に均一に火を通し、煮崩れを防ぎます。
最後に価格です。行平鍋は数百円から数万円まで、様々な価格帯で販売されています。素材や機能によって価格が大きく変わるので、予算に合わせて選びましょう。高価な行平鍋は高機能で長持ちするものが多いですが、使い方やお手入れ方法を守れば、比較的安価な行平鍋でも十分に活躍してくれます。これらのポイントを踏まえて、自分にぴったりの行平鍋を見つけて、毎日の料理をより快適に楽しんでください。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 大きさ |
|
| 素材 |
|
| 取っ手 |
|
| 蓋 |
|
| 価格 |
|
他の鍋との違い
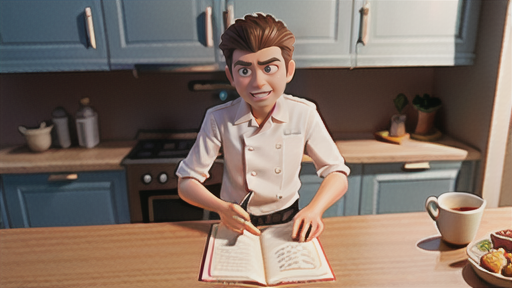
行平鍋は、他の鍋、特に雪平鍋とよく比較されますが、いくつか異なる点があります。まず形を見ると、雪平鍋の底は平らであるのに対し、行平鍋は丸みを帯びた底をしています。この底の形の違いは、それぞれの鍋の得意な調理法に繋がっています。平らな底の雪平鍋は、煮物や汁物など、鍋全体を均一に熱する必要がある料理に適しています。一方、丸みを帯びた底を持つ行平鍋は、一部分を集中して加熱したい炒め物や、とろ火でじっくりと煮込む料理に向いています。
次に、注ぎ口に着目してみましょう。雪平鍋の注ぎ口は片側だけについていることが多いのに対し、行平鍋は両側に注ぎ口がついています。これは、行平鍋が左右どちらの手でも使いやすいように設計されているためです。利き手に関わらず、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質にも違いがあります。雪平鍋はアルミ製が主流ですが、行平鍋は銅製やステンレス製のものもあります。熱伝導率の高い銅製の行平鍋は、食材に素早く均一に火を通すことができます。そのため、短時間で仕上げたい料理や、素材の持ち味を活かしたい料理に最適です。一方、ステンレス製の行平鍋は、耐久性に優れ、お手入れも簡単です。焦げ付きにくく、様々な種類の料理に使うことができます。
さらに、行平鍋の特徴として、打ち出し加工が施されている点が挙げられます。この加工により、鍋の表面積が広がり、熱伝導率が向上します。そのため、食材にムラなく熱が伝わり、美味しく仕上がります。このように、行平鍋と他の鍋にはそれぞれ異なる特徴があります。用途や好みに合わせて鍋を使い分けることで、料理の幅がより一層広がるでしょう。
| 特徴 | 行平鍋 | 雪平鍋 |
|---|---|---|
| 底の形 | 丸底 | 平底 |
| 得意な調理 | 炒め物、とろ火料理 | 煮物、汁物 |
| 注ぎ口 | 両側 | 片側 |
| 材質 | 銅、ステンレスなど | アルミが主流 |
| その他 | 打ち出し加工あり |
